新論説集「マージナリア」運営委員会編集部です。年の瀬いかがお過ごしでしょうか。すこし前のことですが今年の漢字が「税」と発表されました。「税」ではなんとも 味気ない気がしますが、皆様にとってはどのような一年だったでしょう。 第11回の今回は、 三村一貴 (...

Write on Science(理), Literature(文) and Arts(芸)!

新論説集「マージナリア」運営委員会編集部です。年の瀬いかがお過ごしでしょうか。すこし前のことですが今年の漢字が「税」と発表されました。「税」ではなんとも 味気ない気がしますが、皆様にとってはどのような一年だったでしょう。 第11回の今回は、 三村一貴 (...

新論説集「マージナリア」運営委員会編集部です。列島各所の豪雪をニュースに聞き、穏やかならぬ冬をひしひしと感じております...。皆様の御無事をお祈りします。 第10回の今回は、 宮田晃碩 (みやたあきひろ, Akihiro Miyata)『待続――持続の代わりに』 ...

新論説集「マージナリア」運営委員会編集部です。東京あたりは冬紅葉もだいぶまばらになり、豊かに陽を透かすのが美しいような寂しいような趣です。 第9回の今回は、 徳宮博文 (とくみやひろふみ, Hirofumi Tokumiya)『『真理への「病」』と題されたメモ書き』 へ...

新論説集「マージナリア」運営委員会編集部です。めっきり冷え込んでまいりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。(私は風邪を引いておりました...) 今回から第22回まで、 第3号 より「前号への評」を掲載いたします。 第2号 には多くの力作が収録されただけに、それ...
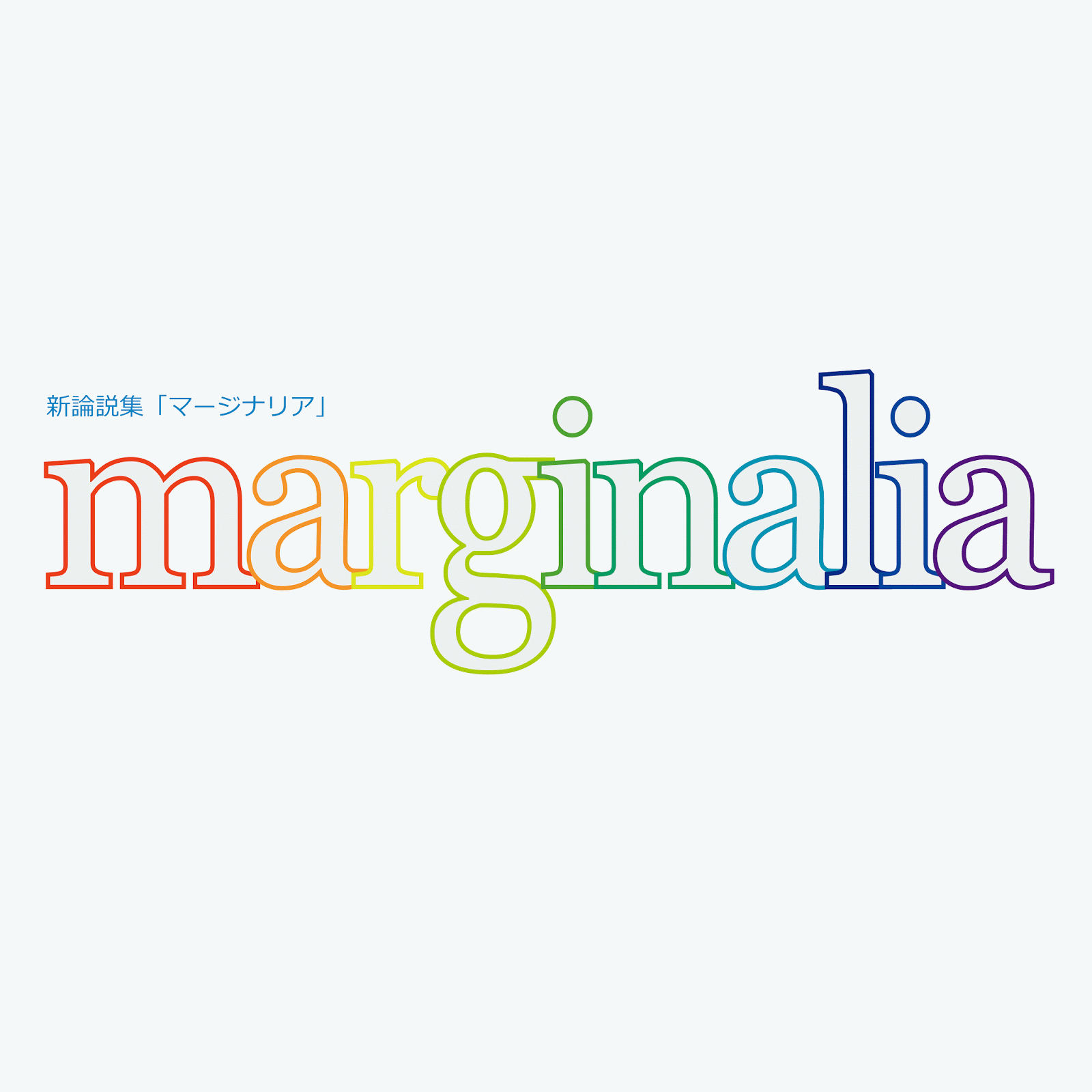
なんということだろう。いまや人間の輝きがすべて降り注ぐような気がする。合唱の意味はここにあったのだ。言語が一なるものを求める、その張りつめた静寂が大音響で、人の体を迸る――。 歌唱の巧拙は私にはよくわからない。歌について常々思うのは、それがいくつかある芸術の分野の...
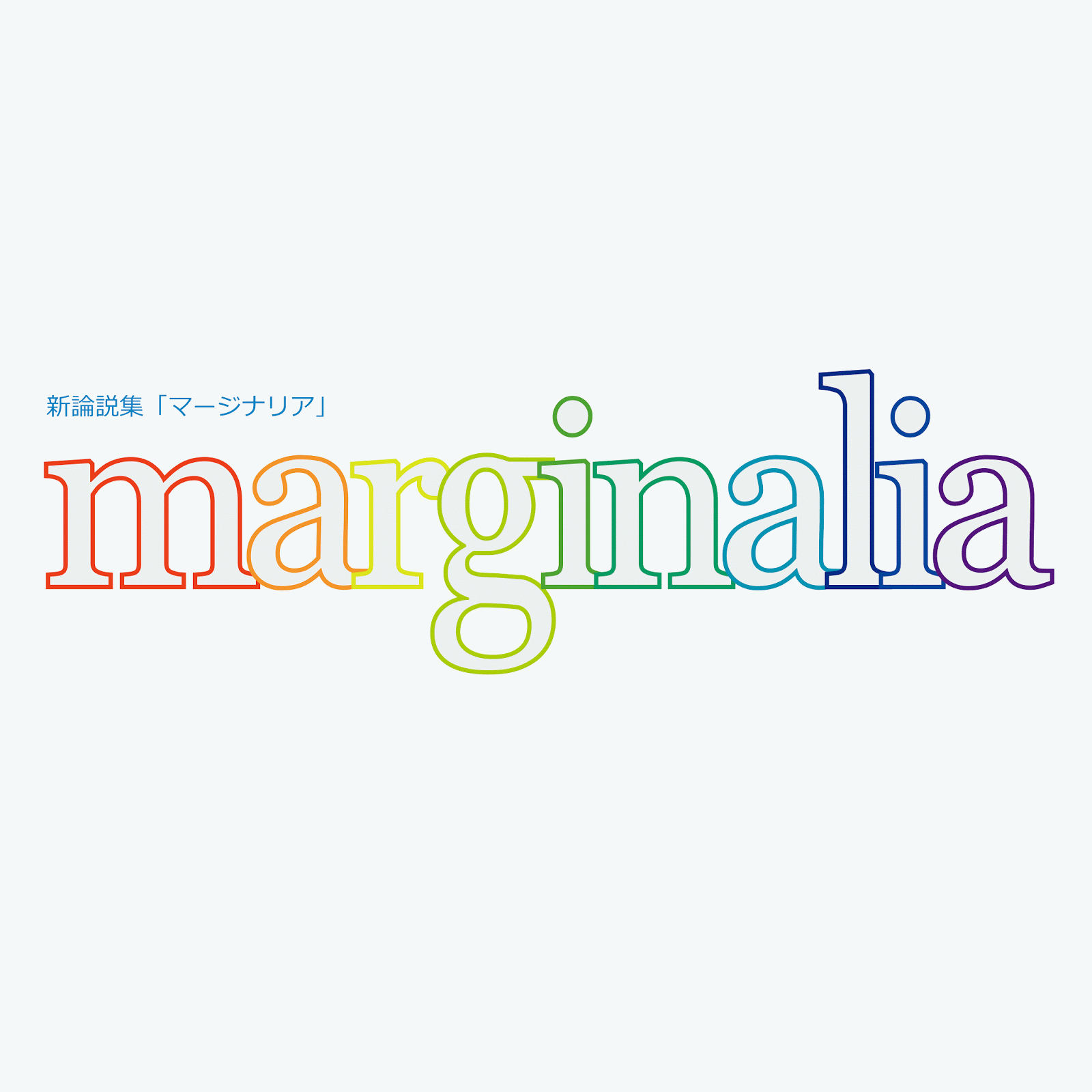
今日、医学部の図書館には当たり前のように日本語の医学の教科書が並んでいる。「岡嶋解剖学」「戸田微生物学」「朝倉内科学」……これらのテキストは版に版を重ね、スタンダードな教科書としての評価を獲得している。私を含む日本の医学生はこうした教科書を通じて ( あるいは間接的に参考...
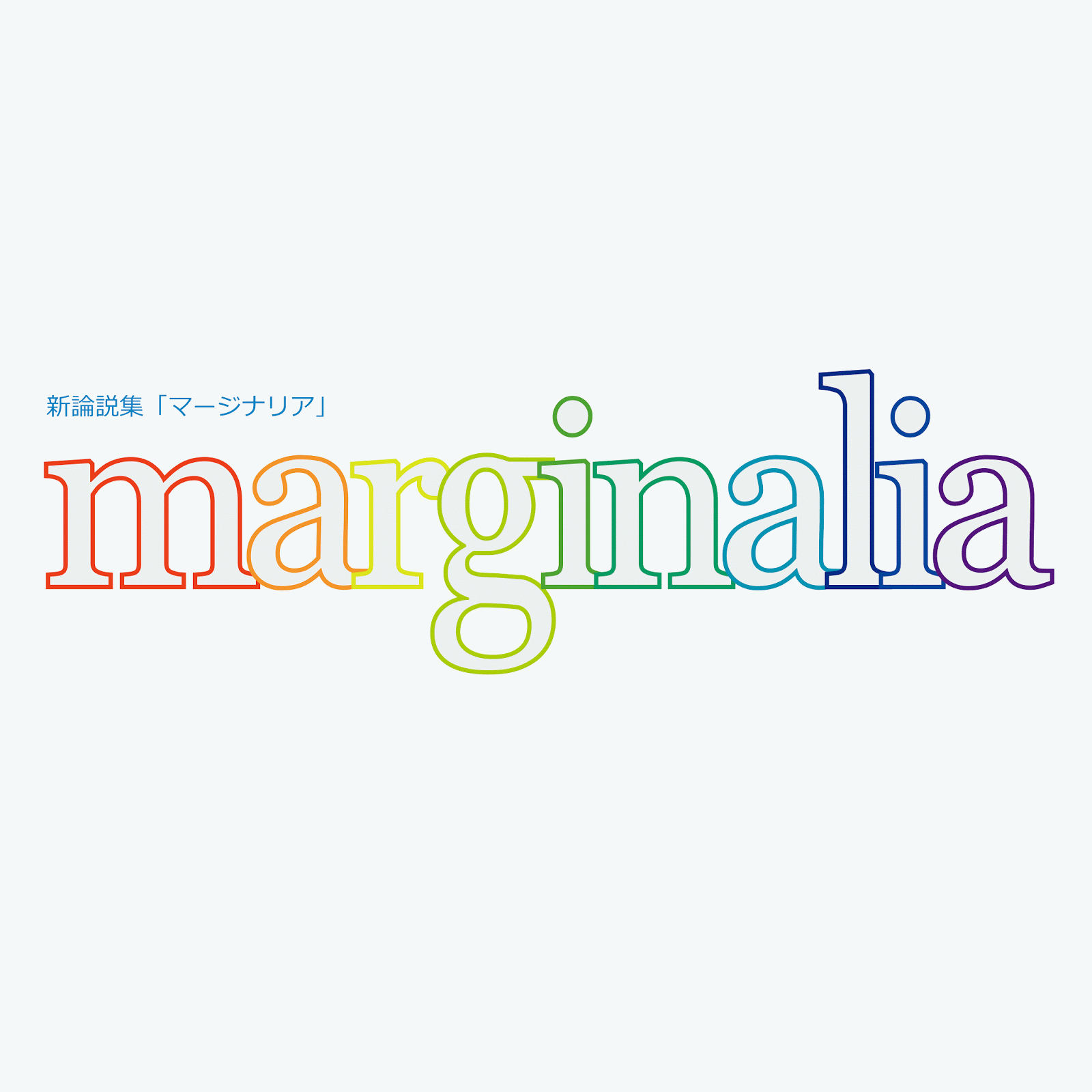
吉村です。 昨今、それなりに知的な人も「基礎理論が一番偉い、応用は現実への当てはめに過ぎないのだ。よって、数学が一番偉い。」という考えを持つ傾向があるように感じます。また、このような考えに基づいているのでしょうか、研究費が削られると聞くと自称理論系の人は「役に立たないから予算を...
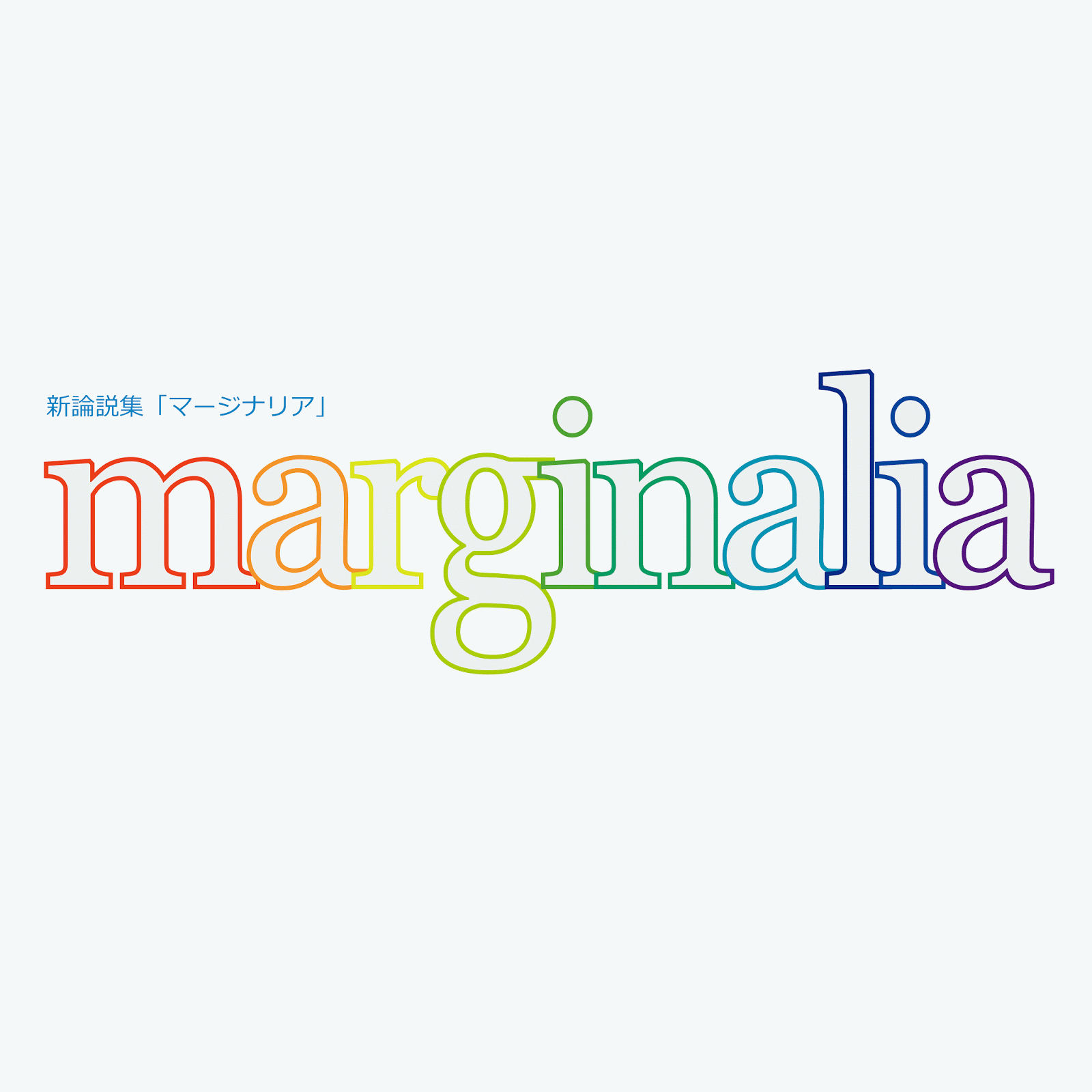
一昨日の会合において、宮田氏は「立秋を過ぎたから、もう夏ではなく秋だ。空も高いではないか。」と言う。しかし私はこれに納得できない。この違いはどこから生じるのか。それは、演繹主義に基づいて考えるか実証主義に基づいて考えるかである。 宮田氏は最初に「立秋」という前提があり、現在...
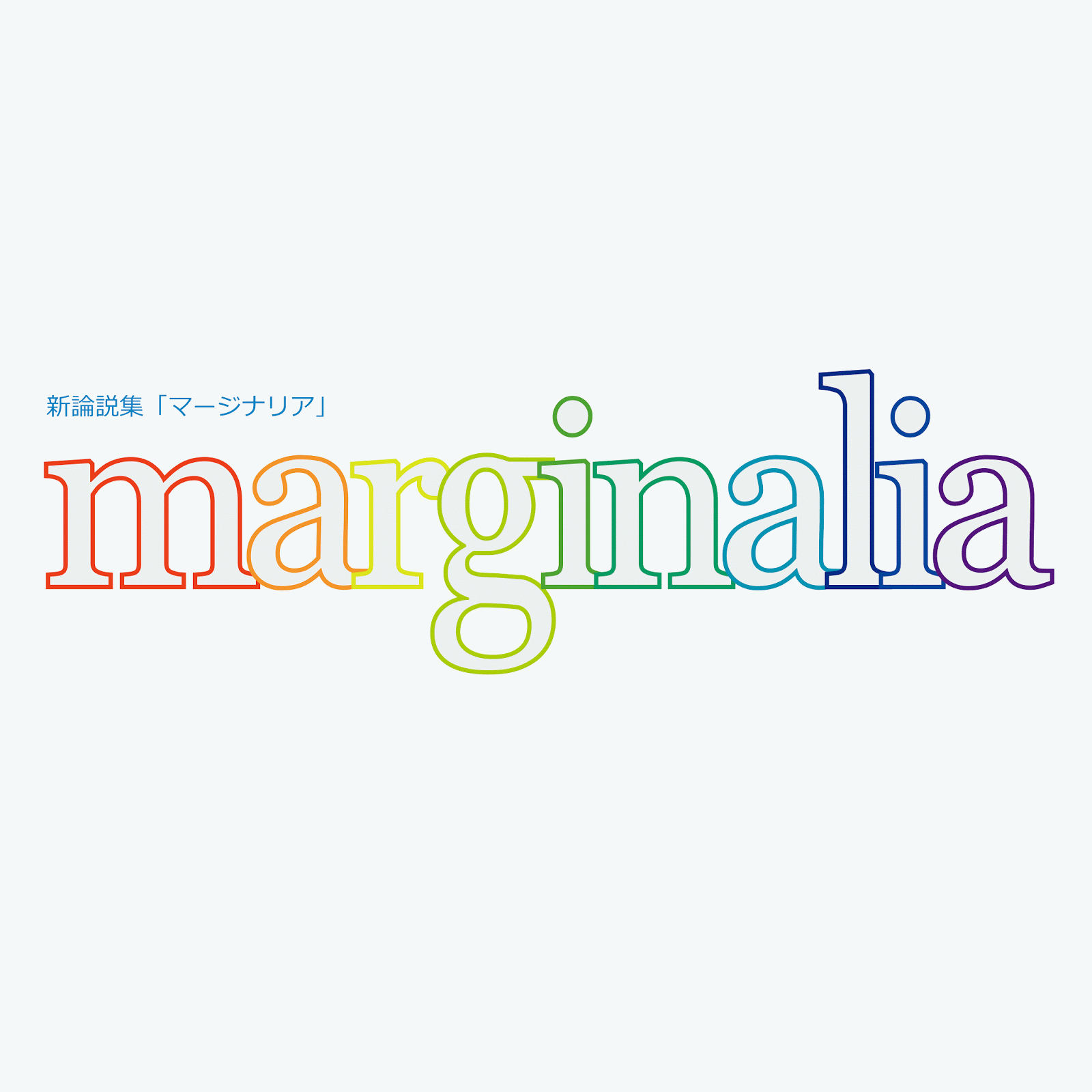
ライン川の向かう岸からワルツが聞こえる。コントラバスの唸り聲は途切れ途切れに、ヴァイオリンの響きはくぐもり、フルートは潑溂と鳴り渡る。これは『アーシャ』の一場面である。 その風土から自然と聞こえてくる音樂があるやうだ。鳥が囀りを、木が葉擦れを、水がせせらぎを持つてゐるやうに、...
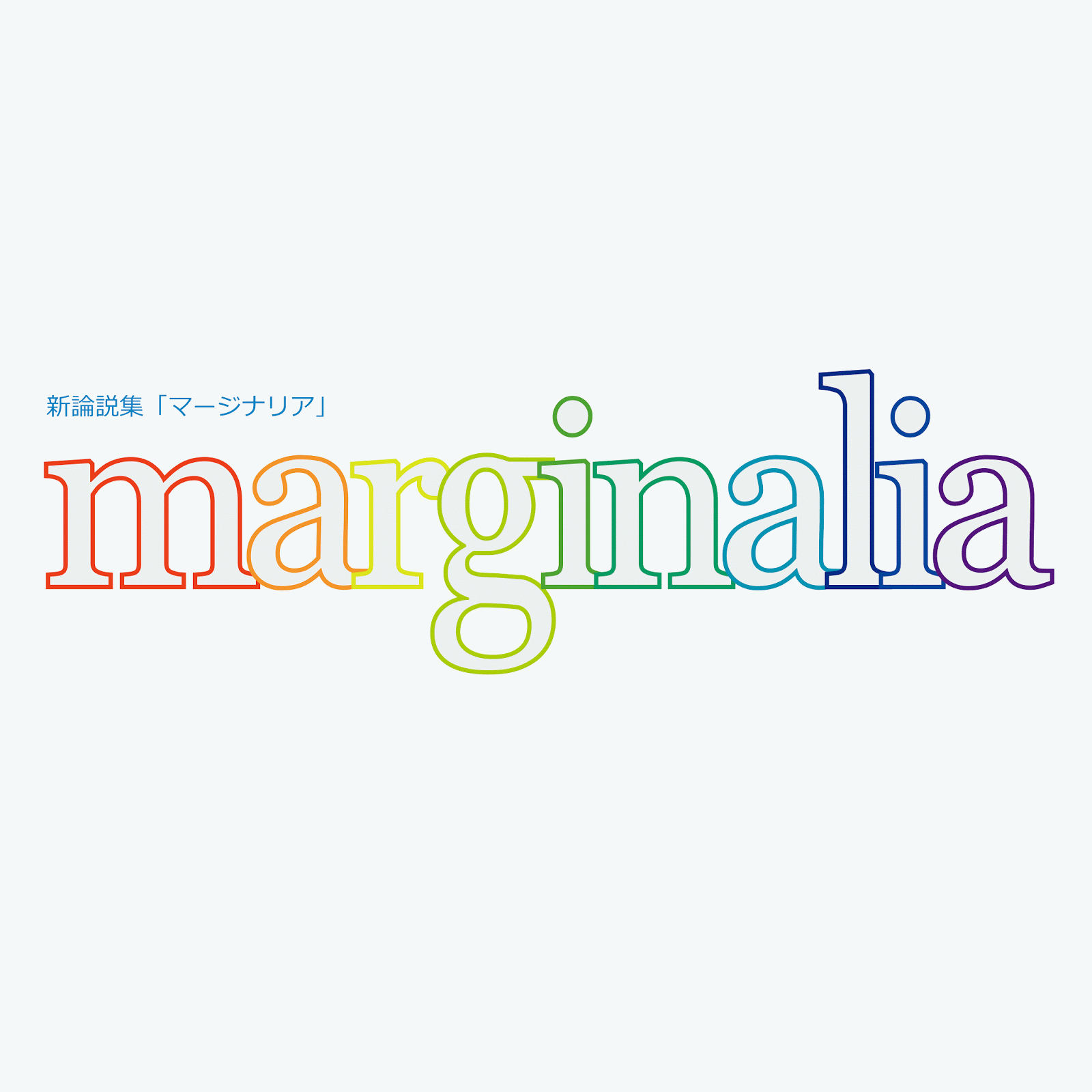
人生の中で忘れえぬ一時期といふものがあるのだらう。しかしその時期の前と後とで自分に變化があるとは限らない。『貴族の巣』のラフレツキーは、物語の終つた後、以前の人生に戻つて行つたと思はれる。『父と子』のアルカージーは結局善良なる紳士として死んでいつたであらうし、『アーシャ』の語り手...
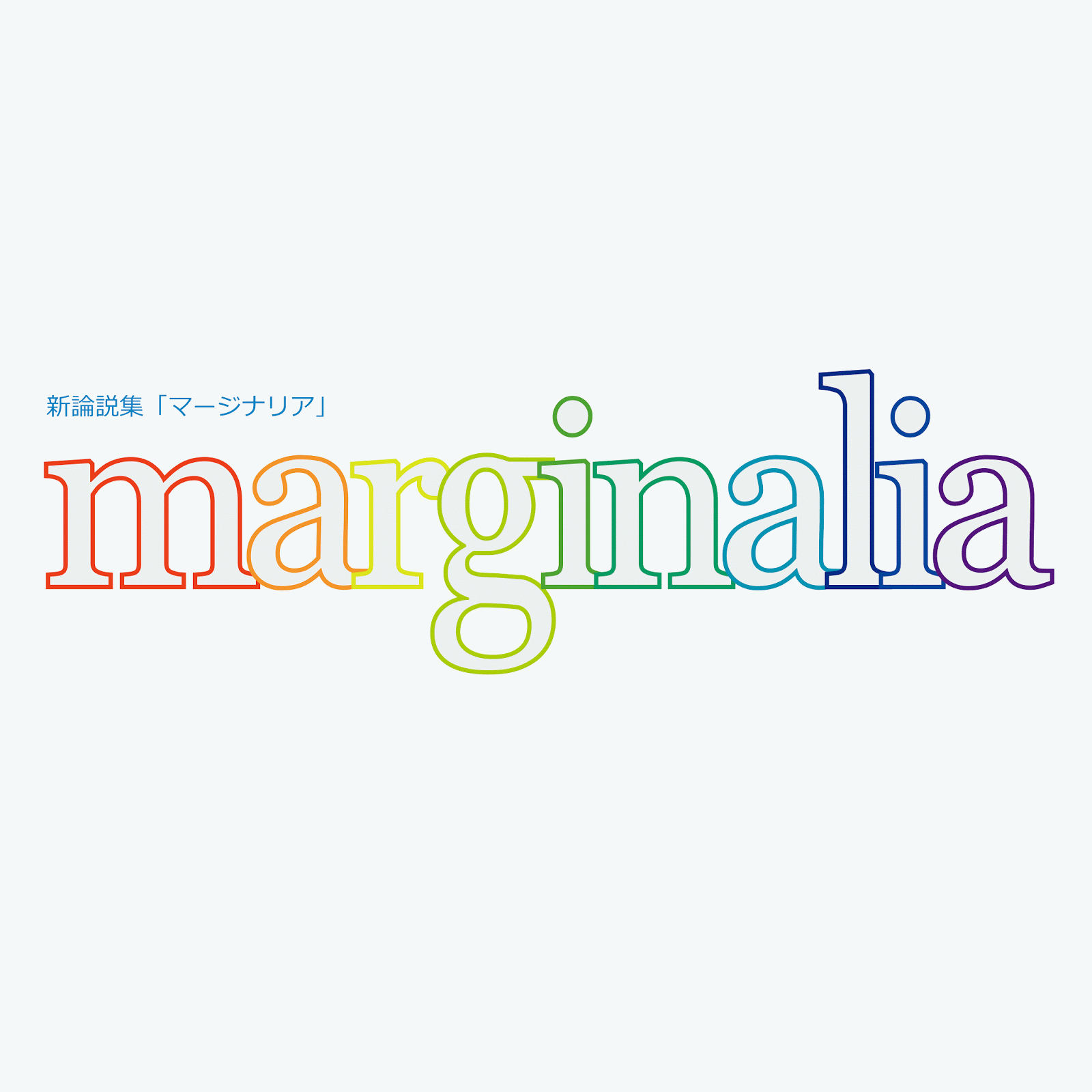
東京國立博物館の東洋館には現在明代の書が展示せられてゐる。そ の中でも陳烈といふ人物の書は、文徴明死して後に没落の道を辿つ た呉派の殘照を見るやうで興味深い。字の形は文徴明や祝允明とさ ほど變はらないのであるが、構成及び雰圍氣が弛緩してゐる。その 原因としては色々考へられる。一つ...